こんにちは、すいかママです。
子供達は、元気に登園してくれ、生活も安定してきたけど小学入学まであと数年。
周りで小1の壁が大変と聞くけど何が大変なの?
うちは大丈夫なの?
何から始めればいいの?
漠然とした不安が襲っていませんか?
かつての私もそうでした。
私は3人(中2、小2、年少)の子育てをするワーママです(夫婦両親は県外在住)。
上の子は育休中でしたが、真ん中は昨年小1の壁を乗り越えました。
上の子の時は、
念願のマイホームを持ち引っ越したばかりで、土地勘や知り合いもいませんでした。
その時の不安はこんな感じでした。
・小学生は朝何時に家を出ているの?
・誰と行っているの?
・学童に入れるの?
・どこにいつ申し込むの?
・何時まで見てくれるの?
ネットで調べても地域ごとに違うため、答えが見つかりませんでした。
2番目の子の時は、
入学までの流れや朝の登下校、学童での過ごし方はある程度わかるけど、それでも不安はたくさんありました。
その時の不安はこんな感じでした。
・仕事をしながらやっていけるの?
・下の子の保育園の送迎もあるけど大丈夫?
・2番目の子は極度の人見知り、近所に同級生がいないけど、小学校や学童に行ける?馴染める
・朝の登下校、上の子は登校班だったけど、2番目の子は個別登校になった。毎朝、出勤前に付き添いが必要?
大変でしたが、色々試行錯誤しながら、仕事を辞めずに 何とか乗り切ることができました。
この記事では、
小1の壁に不安を抱えているワーママに向けて、
小一の壁って何?
何が大変?
対策は?
入学までのスケジュールは?
実際、小1の壁どんな感じだった?
などについてご紹介しています。
小1の壁とは何か?

ウィキペディアによると、
小1の壁(しょういちのかべ)とは、共働家庭や一人親家庭において、子どもが保育園から小学校に入学した際、保育園に預けていた時には実現できていた仕事と子育ての両立が難しくなることを指す言葉である。
小学校入学で仕事との両立が難しくなる理由とは?
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
・放課後の居場所がない
・登校時の見送り
・宿題や家庭学習のサポート、持ち物や時間割のチェック
・学校行事や参観日、面談の多さ
・親子共々、保育園と小学校のギャップに困惑
・長期休みの負担
放課後の居場所がない
保育園は18時頃まで預かってもらえます。
小学校は低学年14〜15時、高学年で16時頃で学校が終わるため、放課後の居場所を考える必要があります。
夏休みなどの長期休暇についても居場所を考えておく必要があります。
一般的によく利用している居場所としては、学童があります。
学童にも以下のような種類があります。
1. 放課後児童クラブ(公立学童):
特徴:
自治体が運営し、小学校に隣接していることが多い。
料金は比較的安価で、おやつ代や教材費などが別途必要になる場合がある。
利用時間:
夕方までの預かりが中心で、延長保育は施設によって異なる。
対象:
保護者の就労状況など、一定の条件を満たす必要がある。
2. 民間学童保育:
特徴:企業やNPOなどが運営し、独自のプログラムやサービスを提供している。料金は公立学童よりも高くなる傾向がある。
利用時間:長時間預かりや、早朝・夜間の延長保育に対応している施設が多い。
対象:就労状況に関わらず、利用できる場合が多い。
地域によっては、学童に入れない、定員オーバーで待機、高学年になると退所となる場合もあります。
登校時の見送り
登校は、地域によって集団登校、個別登校があります。
集団登校であれば、集合場所まで見送ると上級生がサポートしてくれ登校できます。しかし、個別登校では兄弟や 近所の友達がいない場合は一人で登校することになり、最初のうちは親の付き添いが必要になってきます。
出勤時間より登校時間が遅い場合や登校距離が長い場合には、親の負担が増えます。
宿題や家庭学習のサポート、持ち物や時間割のチェック
1年生は、まだ自分で宿題や翌日の準備や管理ができません。
となりで親がサポートする必要があります。
仕事で疲れた、夕食の準備で忙しい、下の子がぐずるなどの時間帯と重なるとバトルになることも多々あります。
学校行事や参観日、面談の多さ
平日の昼間に行事(PTAなども)や授業参観、個人面談があります。
仕事を調整して休む必要が出てくることも職場理解が必要がないとプレッシャーになります。
保育園と小学校のギャップに困惑
保育園と小学校の違いは?
保育園
朝7時から 夜7時まで(長くて)
生活の場:
一人一人の子供の生活、遊び、全体について見てくれて、保護者の様子を毎日伝えてくれていた。
あたたかく成長を見守る場
小学校
教育の場:
学習を中心に子供を指導する
保護者は家庭学習をサポートする必要がある
自立が求められる
集団行動が求められる
保育園と小学校のギャップに慣れるまでは親子共々疲れます。
・子どもの心のケアが必要
学校生活に慣れるまでの不安や緊張があり、帰宅後はグズグス、ダラダラ。
友達とのトラブルも親のフォローがいります。
・親のキャパオーバーで崩壊寸前
仕事、家事、宿題サポート、学校の対応と頭も体も心も疲労困憊になります。
長期休みの負担
春休みや夏休み、冬休みと、学校は休みでも親は仕事。
学童があっても、お弁当持参や利用時間が短いこともある。
朝夕の学童への送り迎えや毎日の弁当作りの生活の変化や負担、ストレスがのしかかります。
また、長期休みの際には学童の開所時間より出勤時間が早い場合、子供を学童入り口で待たせているとも聞いたことがあります。
早めに確認が必要です。
実際、小1の壁はどんな感じだった?
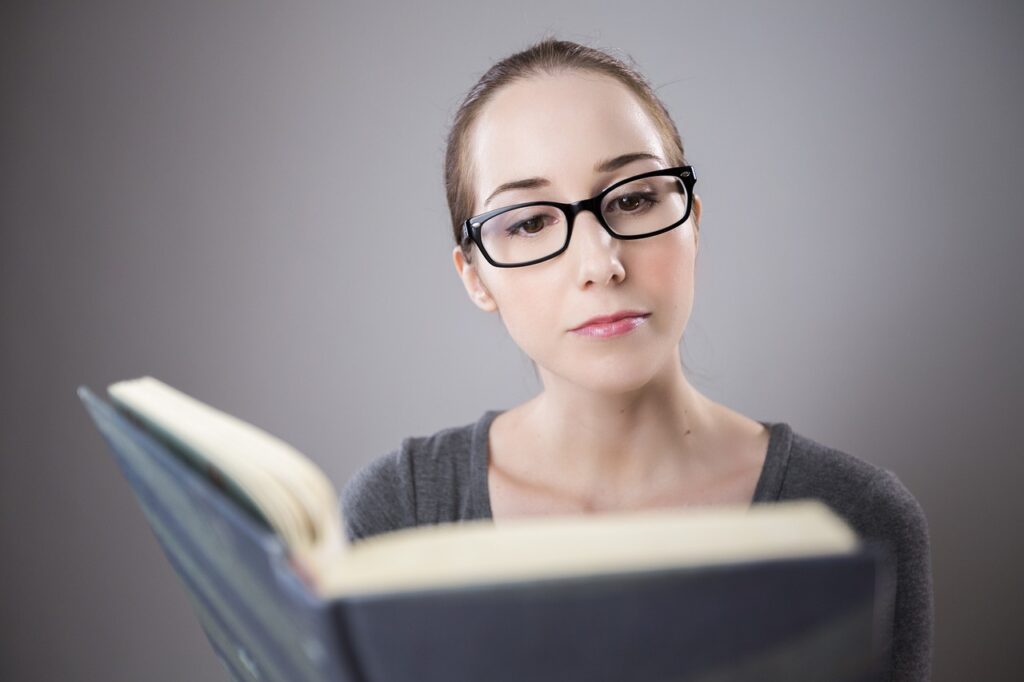
我が家が直面した壁、大変だったこと
どんな準備をした?

上の子の時は、引っ越した直後で知り合いもおらず、小学校の情報が全くなかったので、入学までや入学後の流れやイメージがわからずとにかく不安でした。
その時、我が家が準備したことはこんな感じでした。
どれも最低限やっていて良かったです。
①小学校までの登校距離が徒歩30分と遠方で不安だったので、近所の子は、何時に学校へ出発しているか、注意深く観察しました。
②近所の公園に遊びに来ている小学生に声をかけ、学校のこと(制服なども)や登校のことについて聞きました(ついでに仲良くしてねとも声をかけました)。
③地域の子供会に入り、大人からも情報を集めました。すると、登校班の集合場所や登校ルートがあることがわかりました。制服のポロシャツやスカートは学校での購入だけでなく、市販の物でもいいと知りました(小さなことですが学校購入より安く準備できました!)。
④体力が必要だと思い、年長よりプールを習い始めました。
⑤入学後、読み書きなど授業についていけるように年中から進研ゼミを始めました。
⑥市の広報誌に学童一覧を見つけ、小学校隣接の学童に連絡しました。開所時間や土曜日の利用(仕事が土曜日もあるので)、入りやすさなど、仕事が続けられそうかに必要となりそうな情報収集しました。
⑦上の子の時は育休中、2番目の子の時はフルタイムでした。2番目の子の時には、育児時短勤務が利用できたので3カ月程度利用しました。夕方は仕事が16時までだったため、子供の心のケアや宿題・持ち物チェックのサポートが余裕をもってできたので良かったです。
我が家の小1の壁、実際どうだった?
・放課後の居場所がない。
→学童が利用できたため、仕事を辞めずに続けることができました。
・登校時の見送り
→上の子の時には、集団登校だったので、集合場所に1週間ほど付き添うと、後は上級生が連れていってくれて助かりました。ただ、集合時間に遅れないように気をつかいました。
2番目の子の時には、個別登校に変わり近所に一緒に行ける友達もおらず(姉は卒業してました)、入学から2ヶ月半くらい登校時の付き添いをしました。下の子連れての付き添いは(ベビーカーで往復1時間・・・)、限界で途中で夫に交代してもらいました。
入学当初は、朝の行きしぶりがひどく、朝行きたくない、玄関で大泣きなどバトルがあり、肉体的・精神的に疲労困憊でした。
・宿題や家庭学習のサポート、持ち物や時間割のチェック
・宿題や家庭学習のサポート
→学童で、一部宿題を済ませて帰ってきていました。しかし、計算カードや音読は学童ではみてもらえないので、帰宅してからします。帰宅した途端、子どもはダラダラして中々はかどりません。一人でもまだ進まないので隣で励ましながらサポートする必要がありました。習慣化しないと、後々大変になるため、忙しい夕飯時ではありましたが忍耐強く付き合いました。イライラすると子どもは余計に進まないので、とにかく穏やかにしたかったけどそうはいかない日もあり、きつかったです。
また、上の子の時には、先生が宿題を丸つけしてくれていましたが、2番目の子の時には、宿題の丸つけも親がすることに変わっていました。少しのことですが、忘れることもあったり大変でした。
・持ち物や時間割のチェック
→翌日の時間割を書いていなかったり、急に算数で空き箱が必要、図工でモールやリボンがいるってこともあり、就寝前になって慌てて準備することもありました。
・学校行事や参観日、面談の多さ
→うちの小学校ではこんな感じでした。
個人懇談:4月下旬、7月中旬、12月中旬
参観日:4月下旬(個人懇談と同時期でげっそり・・・)、6月、9月
行事:遠足5月、運動会10月、学習発表会1月
これに加え、我が家は中学校や保育園の懇談や参観日、行事・・・各々の歯医者など次から次へとイベント。子供が体調崩すこともあったりして、休みのやりくりが大変でした(泣)。
・親子共々、保育園と小学校のギャップに困惑
→朝の早起きや宿題・学校の準備、友達関係・・・。保育園卒園から小学校入学と2週間ほどで大きく環境が変わり、子供には自立が要されます。子供が学校生活に慣れるまで親子ともども疲労困憊でした。
・長期休みの負担
→長期休みでは、学童の毎日のお弁当作りや朝の送迎に負担が増え大変です。お弁当は、作る手間やレパートリーに悩まされました。朝の送迎は、学童から保育園とはしごになるため、必然的にいつもより早く家を出る必要があり、朝からイライラして大変です。長期休み明けもまた生活に慣れるまで、親子ともども忍耐が必要です。
対策は?

とにかく、早めに入学の流れを知り、情報収集、我が家の小1の壁を乗り越えるイメージをつくる!に尽きると思います。
・学童の早期確保・見学
もし学童が難しそうであれば、ファミサポ、祖父母、民間サービスを組み合わせることも検討する
・登下校の練習
・生活リズムの切り替え、読み書きの練習を前倒しで行う
・会社への調整依頼(時短・在宅・勤務時間の変更)
小学校入学までのスケジュールは?

(地域によって誤差があると思います。うちの地域では・・・。)
【8月〜9月】
・就学に関する通知が届く(自治体による)
市区町村から「就学時健康診断のお知らせ」が届き始めます(自治体によっては10月以降)。
学区・通学予定の学校を確認。
学童保育の情報収集を始めておくと◎。
【10月〜11月】
・ 就学時健康診断
指定された日に小学校で健康診断(視力、聴力、内科、歯科など)。
学用品、入学式の詳細、提出書類などが説明される。
制服や体操服のサイズ合わせ、学用品の展示、注文書をもらいました
※学校からの説明時に、学童の案内がありました。説明の帰りに、早速学童へ行き、申込書をもらいました。
・学童保育の申込(必要な場合)
※うちの場合10月末が締切でした。
利用希望者は早めに申込(自治体や施設によって受付時期が違う)。
募集が多い地域では「抽選」の場合も。
【12月〜1月】
・ 入学説明会の案内が届く
通学する小学校から入学説明会のお知らせが届きます。
※うちの場合、11月に学童利用可の通知が届き、12月に学童の面談がありました。
【2月】
・ 1日入学、説明会に参加
子供たちは、上級生にリードされて、教室へ行って体験しました。
保護者には、学用品リスト・通学路・PTA・給食などの具体的な案内がある。
・学用品などの準備スタート
持ち物指定が細かいので、購入は説明会後がおすすめ。
※うちの小学校の筆記用具のきまり
鉛筆(Bまたは2B)・・・4.5本
6B鉛筆・・・1本
赤鉛筆・・・1本
青鉛筆・・・1本
消しゴム・・・1個
ものさし(10~15cm程度)・・・1本
ネームペン(油性)・・・1本
(禁止)シャーペン、ロケット鉛筆、飾り付きの鉛筆、蛍光ペン、ラメ入りボールペンなど
※ランドセルは、上の子の時には10月、2番目の子の時には6月に購入しました。上の子の時にはじっくり吟味したい・購入した後に違う色がいいと言ったらどうしようなど悩み、ゆっくりでした。しかし、10月頃には同級生が徐々にランドセルを買ったと聞き始め、ランドセルがなくなると、最後は焦り購入しました。2番目の子の時には、余裕を持って早めに準備しました。
【3月】
・ 保育園・幼稚園の卒園
卒園式、アルバム、お別れ会などで多忙。
子どもの気持ちのフォローを意識して。
・ 小学校生活の練習
登下校の練習(実際の通学路を歩く)
・算数セットなど細かい物の名前つけ。おはじき一つ一つまでかなり細かく、疲れるので早めに少しずつ始める方が無難です。
【4月】小学校入学!
・学童は、4月1日よりお弁当を持ってスタート。
※卒園後、1週間ほど保育園で預かって頂いて、4月1日から急に学童の利用が始まったため、子供も親もギャップへの困惑は大きかったです。
・入学式に参加。翌日から歩いて登校も開始。本格的な学校生活がスタート。
最初の1〜2週間は**午前授業(短縮)**の場合が多く、親のサポートが引き続き必要
「小1の壁」仕事が続けられそうか チェックリスト

【時間・スケジュールのチェック】
□小学校の下校時間に間に合う勤務スケジュールか
□ 学童保育に入れる見込みがある
□学童保育の終了時間までにお迎えに行ける
□ 夏休み・冬休みなど長期休みに対応できる体制がある(休暇や在宅勤務など)
□ 時短勤務・在宅勤務などの柔軟な働き方が可能
【子どもの生活・サポート体制】
□ 子どもが一人で登下校できそう
□子どもが学校での生活にある程度適応している(疲れすぎていない、登校しぶりがない)
□ 自宅で子どもがある程度一人で過ごせる時間がある(鍵っ子にしても安心できる)
□ 家族や近隣に頼れる人がいる(急な発熱やトラブル時のサポート)
【職場の理解・柔軟性】
□ 会社に「子どもの都合で早退・欠勤」への理解がある
□ 緊急時(学級閉鎖・突然の下校など)に対応できる体制がある
□ 働くママやパパが多い職場で、情報共有や相談がしやすい
□有給を取りやすい雰囲気がある
【自分の気持ち・覚悟】
□ 仕事と家庭のバランスをとりたいという意思がある
□ 子どもに対して「100%完璧な母親」を目指しすぎていない
□ 「できないことは頼る」「無理なら環境を変える」という柔軟さがある
□ 一時的に働き方を見直す(時短・転職など)選択肢も視野に入れている
チェックが多いほど「続けやすい」傾向があります。
⚠ チェックが少ない項目は、事前に対策を考えると◎(例:ファミサポ登録、在宅勤務の導入など)。
100%完璧を目指すのではなく、「どうすれば続けられるか」の視点で柔軟に考えるのがポイントです。
☆完璧を目指さなくて大丈夫です。
小1の壁は「親子の転換期」でもある
不安があるのは当然。焦らず、頼れるものを使ってOK
仕事も家庭も「続ける」ための柔軟さを持つことがカギ
まとめ

「小1の壁」は、ひとりで抱えなくて大丈夫
小1の壁に不安を感じるのは、あなたが「子どものこと」「仕事のこと」「家族のこと」を真剣に考えている証です。
小学校に上がると、保育園とはまったく違う世界が始まり、親にも新しい役割や調整が求められます。
でも、それはあなただけではありません。多くのワーママが同じように悩み、少しずつ「自分たちのやり方」を見つけて乗り越えています。
大切なのは、完璧を目指しすぎないこと。
早めに流れを知って、少しずつ準備することで不安が少し和らぎます。その時その時の対応でも何とか乗り越えられたりします。
すべてを一人で抱えず、頼れる人やサービスを使って、“自分たちのペース”で進むことが、何よりの対策です。
不安な気持ちを否定せず、「大丈夫、やっていける」と自分に声をかけてあげてくださいね。
あなたとお子さんの新しい生活が、笑顔でスタートできますように。
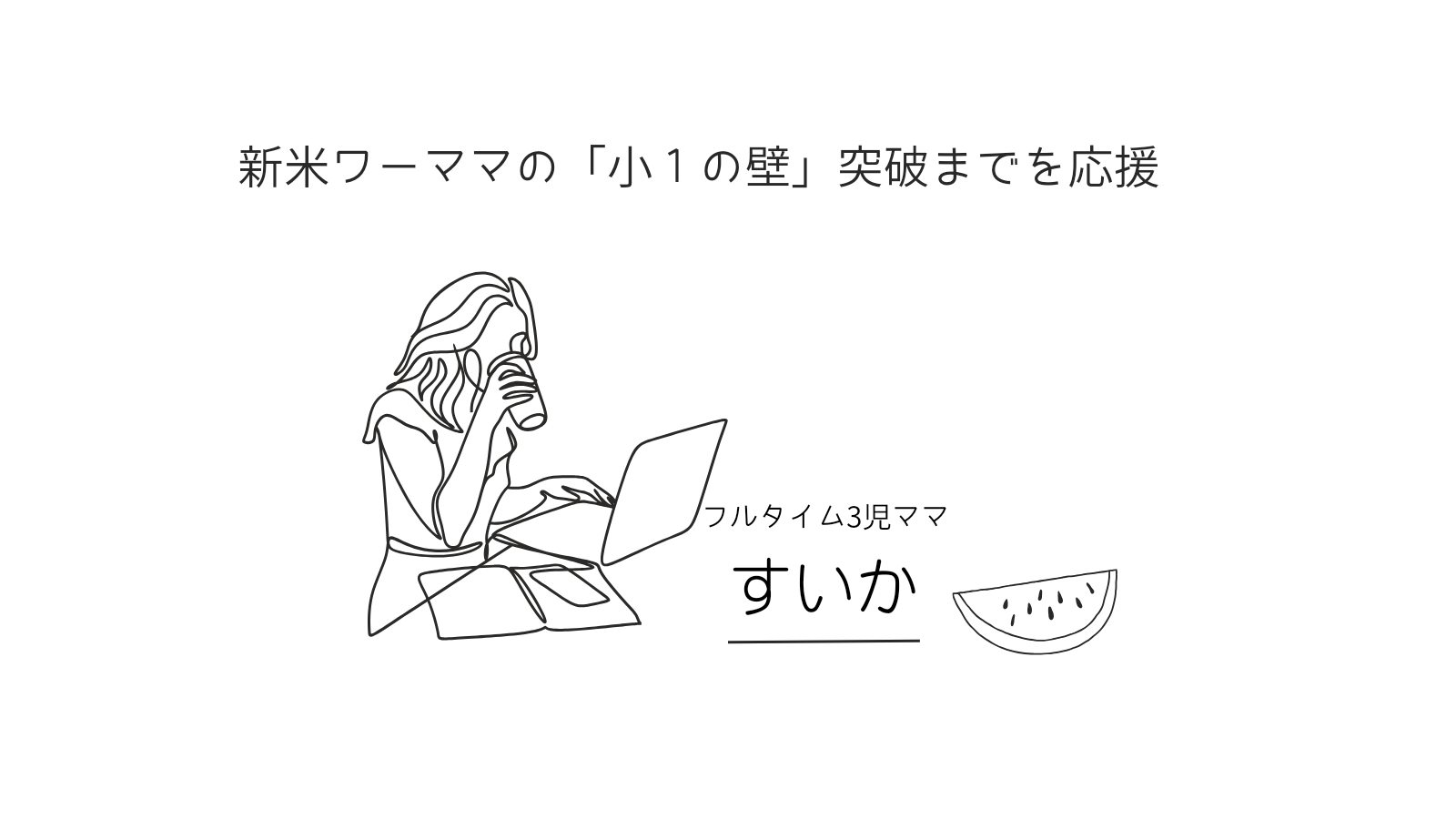
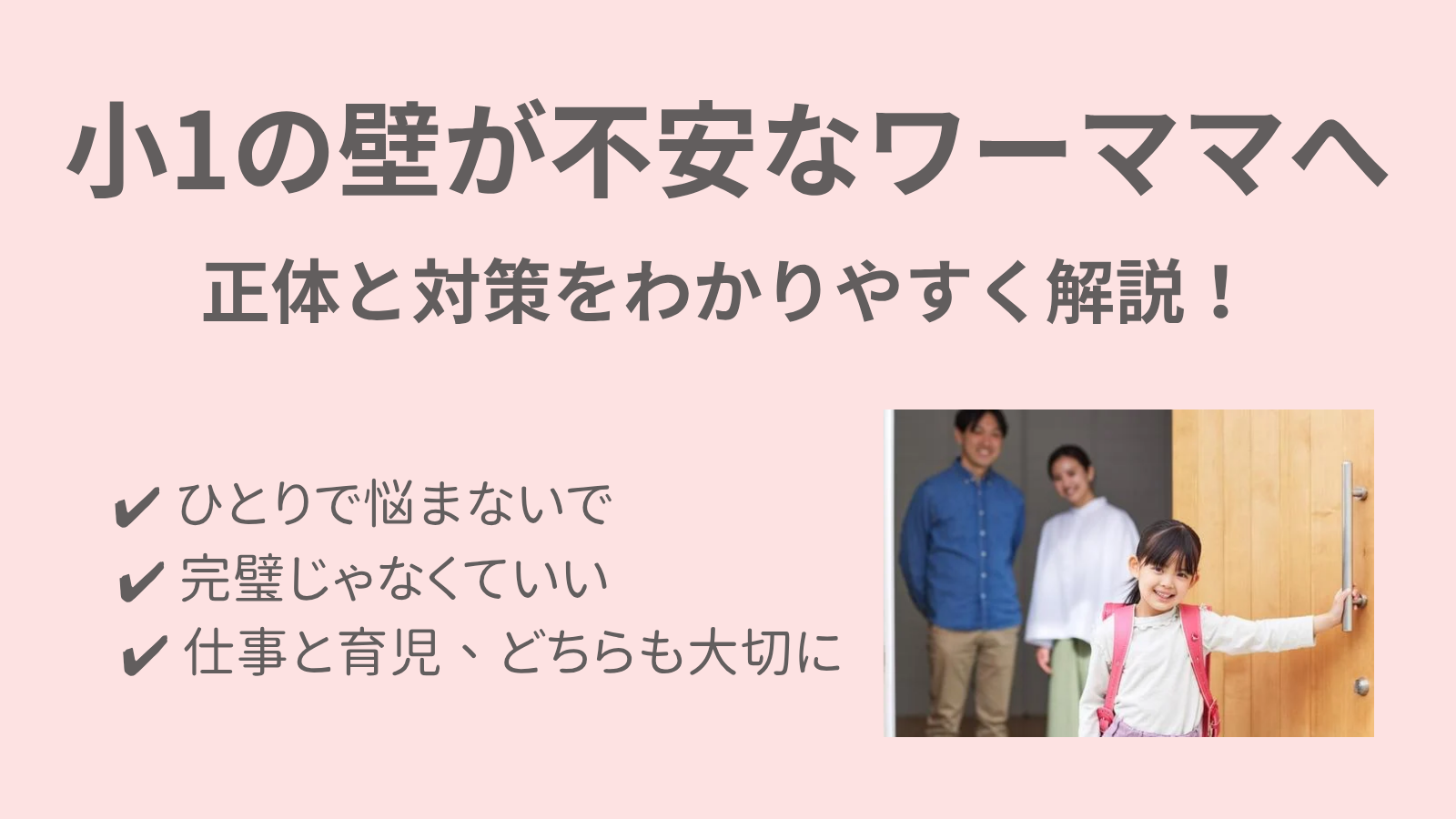
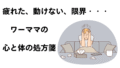
コメント