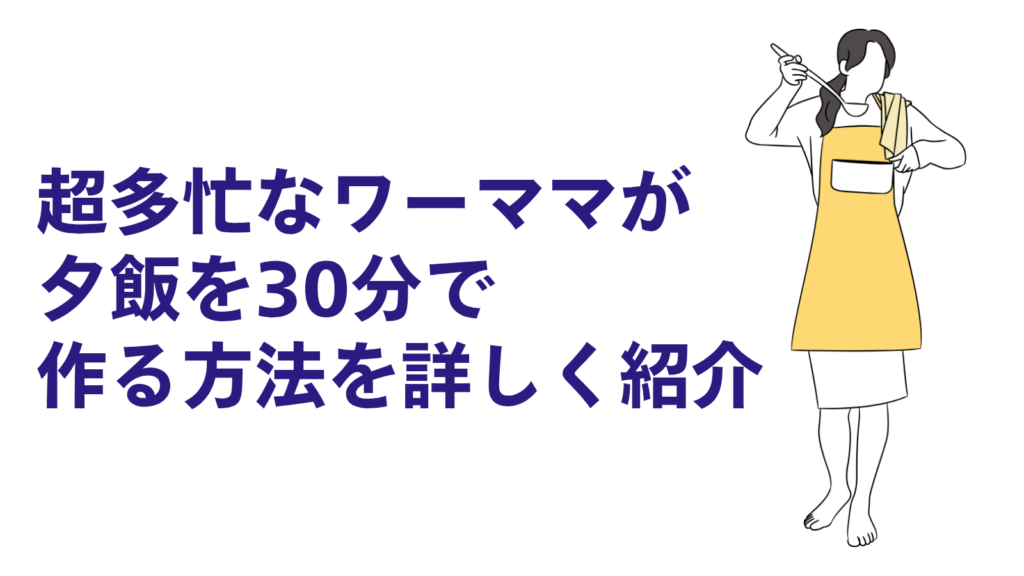
こんにちは、すいかママです。
平日の夕飯作り、ヘトヘトでもう作れない。
帰宅してパパっと夕飯の準備できないかな。
ワーママは、いつ夕飯を作っているの?
そんな悩みはありませんか?
かつての私もそうでした。
私は、もう10年以上フルタイムで働く3人の子育てママです。
子育てしながらの毎日の夕飯を作ること、ワーママである最大の試練かもしれません。
新米ワーママ時代の私は、夕飯作りが気になり、子どもが遊んで家に帰ってくれないことに、よくイライラしていました。我が子との時間大事にしたい、もっとおおらかな母になりたい、、、色々試行錯誤し、今のスタイルに落ち着きました。
今回は、忙しい新米ワーママに向けて夕飯を30分で作る方法をわかりやすく解説していきます。
この記事は、こんな方にオススメです。
帰宅後30分で夕飯を作りたい
ワーママがいつ夕飯を作っているか知りたい
夕飯を30分で作る方法
献立を考える

毎日の献立を考えることは本当に大変です。
一週間分まとめて献立をたてる家庭をあるよですが、私には面倒でこの方法に落ち着きました。
我が家の献立は、主菜と副菜2〜3品、汁物です。
方法はこんな感じです。
①メイン素材を決める②メイン素材の調理方法を決める③副菜、汁物を決める
メイン素材を決める
メイン素材をパターン化する
曜日ごとに肉や魚、丼ものなど、固定化すると、夕飯の献立に悩まず、楽に決められるようになります。
例えば、月曜は鶏肉、火曜は魚、水曜は丼ものやカレーなど、木曜は魚、金曜は豚肉、土曜は鍋やホットプレート料理、手巻き寿司など、日曜は野菜炒めと焼き魚などと決めておきます。
少しパターンがあるだけで、ストレスが減ります。

我が家は、1週間にメインとなる肉や魚の食材を8〜9つ程度買います。
その食材を1週間で使い切るように献立を立てるようにしています。
メイン素材の調理法を決める
お肉や魚などメイン素材を決めると、
味付けを和洋中したり、
調理法を焼く、蒸す、煮る、揚げるなどを組み合わせると比較的バリエーションがもてるようになります。
事前に自分でメイン素材ごとの作りやすいメニューをあげておくと、調理手順にも悩みにくくスムーズに進みます。
我が家の素材ごとの作りやすいメニュー
| 豚 | 牛 | 鶏 | ひき肉 | 魚 | |
| 焼く、炒める | 生姜焼き 野菜炒め キムチ炒め 野菜巻き ポークチップ トンテキ ソテー | オイスターソース炒め チンジャオロース | 照り焼き 甘酢あん 味噌漬け焼き | つくね 餃子 ハンバーグ 麻婆豆腐 | 塩焼き ムニエル マヨネーズ焼き ホイル焼き チーズ焼き |
| 蒸す、煮る | 豚しゃぶ 豚の角煮 | 肉じゃが すき焼き風煮物 | 手羽元煮 | ロールキャベツ | 煮つけ ぶり大根 |
| 揚げる | とんかつ 酢豚 | 唐揚げ チキンカツ 油淋鶏 | コロッケ メンチカツ 蓮根はさみ揚げ ピーマンの肉詰め | 竜田揚げ 南蛮漬け フライ | |
| オーブン | スペアリブ | バジル焼き | |||
| 一品料理 | 豚丼 お好み焼き 焼きそば かつ丼 | ビーフシチュー カレー 牛丼 ハヤシライス | ドライカレー 三食丼 ミートソースパスタ チャーハン | かば焼きドン 鮭寿司 たらこパスタ |
副菜、汁物を決める
野菜の中からサラダや和え物、煮物など自身の作りやすい定番の副菜を複数リストアップしておくといいです。
きゅうりやトマトは切って出すだけでいい食材で便利です。
レンコンやかぼちゃなど素揚げするだけでもボリュームが出て一品になります。副菜は、多めに作り翌日にも食卓に出したりしています(翌日に副菜をもう1品作れば、それで副菜2品。野菜が沢山とれます)。
汁物は、メインと副菜で使用しなかった野菜を入れて味噌やコンソメ、中華スープの素で味をつけると、いろんな野菜がとれてバランスも良くなります。
料理工程を効率化する

まな板が汚れにくい食材から切る
包丁とまな板を洗う作業を減らすためにできるだけまな板を汚さないように工夫します。
サラダ用の野菜などまな板が汚れにくいものから切り、その後に肉や魚を切ります。
野菜は、汁用、炒め物の用などその先の料理をイメージして一度に量を切り分け、用途別に取り分けておきます。そうすることで何回も切る手間が省けます。
ポリ袋を使い、調理や保存をする
下味をつける時は、ポリ袋に調味料や片栗粉などを入れ、その中に食材を入れればお皿や手を汚さずにまんべんなく混ぜられます。そのまま冷蔵庫にも保存ができます。

我が家はポリ袋は、アイラップという商品を使っています。
アイラップは、そのまま電子レンジにかけることができます。
じゃがいもやさつまいもなどの野菜は、少し濡らし、電子レンジでチンするだけであっという間に蒸し野菜が作れます。
同じフライパンと湯でアクの少ないものから茹でる、焼く
同じフライパンで茹でたり、焼くことで洗い物が減ります。
鍋やフライパンは大きくて場所を取ったり、洗いにくいのでできるだけ少しの数で済ませると時間とストレスが減ります。

我が家は、深めのフライパンを使用することが多いです。
底面積の広いフライパンを使うとお湯が沸くのが早く、長い青菜を入れる時に少量の茹ですみます。
サラダや 和え物用のキャベツ、人参、ブロッコリー、小松菜などの順に茹でます。その後はフライパンを水でささっと洗います。そして、油を引いて焼き物用フライパンとしても使います。
朝の下準備をする

少し早起きして朝の時間に、調理の下準備をしておきます。
帰宅後に焼くだけ、煮るだけ、和えるだけにしておくと、かなり時間短縮になります。
私は、こんな感じで準備しています。
・調理に必要な野菜を切っておく。
・野菜を茹でて、絞っておく。
・メイン素材(時には野菜も一緒に)をポリ袋に入れて下味をつけておく。
時短だけでなく、素材に味もしみ込むため子供たちは、美味しいとパクパク食べてくれます。
・汁物は、切った野菜とだしや中華スープを鍋に入れてセットし冷蔵庫で保存しておく。
帰宅後には、水を入れてタイマーをかけて煮るだけ。
朝は、朝食の準備のために台所に立ちます。
そのタイミングで夕飯の準備を半分しておくと、夕方の貴重な時間の短縮になったり、ストレスの軽減になります。
朝も野菜を切ったり、下味つける程度なのでそんなに大変ではありません。
夕方もタイマーつけながら焼いたり、汁物を煮たりする程度なので、その間に食洗器の中を片づけたり、子供の宿題や翌日の準備を見たりと、時間を使うことができます。

仕事に復帰直後で、子供が小さいと夕方かなり子供に手をとられます。
そんな時期は、朝の時間帯に焼いたり、煮たりし、夕方は温めるだけの状態までしていました。
小さい子は、予期しないハプニングや片づけ、掃除なども多いため、朝の段取りはかなり重要でした。
我が家のタイムスケジュール

5:00 起床 洗顔・メイク
5:20 風呂掃除、洗濯物を乾燥機から出し畳む
5:40 朝食、夕飯半分、夫の弁当準備
6:20 子供起床(三女手がかかるので6:40ぐらい)
6:45 朝食
7:20 次女登校(長女は7:50)
7:30 夫出勤
7:40 私の出勤(三女保育園へ8:00に送る)
17:30 私の退勤
17:50 三女保育園迎え
18:10 次女学童へ迎え
19:00 夕食
20:00 入浴
20:30 夫帰宅
21:30 子供と就寝
こうしてみると、かなりワンオペ・・・。両親も県外なので頼れず・・・。
とにかく、作りたくない日の乗り切り方

準備5分、電気圧力鍋を使って後はほったらかし料理
カレーやシチュー、 親子丼は、材料を切って電気圧力鍋に入れてスイッチを入れるだけでほったらかしにしてご飯ができます。
最初に準備だけすれば、キッチン周りの片付けや子供のお世話に時間が使えます。
頭を使わなくてできる料理なので疲れた時や 時間がない時の我が家の定番料理です。
冷凍食品
コープの焼くだけ冷凍食材や楽天マラソンで購入した大容量の冷凍餃子、ふるさと納税で購入した冷凍ハンバーグは、我が家の救世主料理です。
美味しくて子供も大好きです。
惣菜
仕事が遅くなり、体力的に限界の時にはスーパーでお惣菜を買って帰ることもあります。
家族みんな笑顔で食べればいいかと、もう割り切る日もあります。
麺、レトルト
災害時の備蓄も兼ねて麺や牛丼や中華丼、親子丼、カレーなどのレトルトや麺類をストックしています。ママが体調を崩した日でも乗り切れます。
ミールキットを利用する
食材とレシピがセットになっている商品のことです。食事の下処理やカットが既にしてあり、使う調味料が一緒に入っているのでレシピ通りに調理するだけで簡単に美味しい料理を作ることができます。ヨシケイやオイシックス、コープデリなどがあります。
調理方法も簡単で洗い物が少なく、後片付けも楽、何といっても献立を考えなくていいため、ストレスはかなり減ります。
まとめ

今回の記事では、忙しいワーママに向けて夕飯を30分で作る方法をわかりやすく解説しました。
今回のポイントをまとめますと次の通りになります。
・献立をパターン化した方法で考える
・料理工程を効率化する
・朝に下準備をする
どうしても、疲れたーと、作りたくない日は、次のような方法で乗り切ります。
・準備5分、電気圧力鍋を使って後はほったらかし料理
・冷凍食品
・惣菜
・麺、レトルト
・ミールキットを利用する
今までよりは、夕飯を短時間で作る方法やアイディアが少し生まれたのではないでしょうか。
夕飯が短時間で準備できることで、空いた時間で子どもと一緒に過ごすことが増えたり、自分のしたいことができるようになります。時間ができることで、心にゆとりができます。ニコニコしていることが増えると、子供も嬉しくなるものです。そして、家族のコミュニケーションも増えてきます。
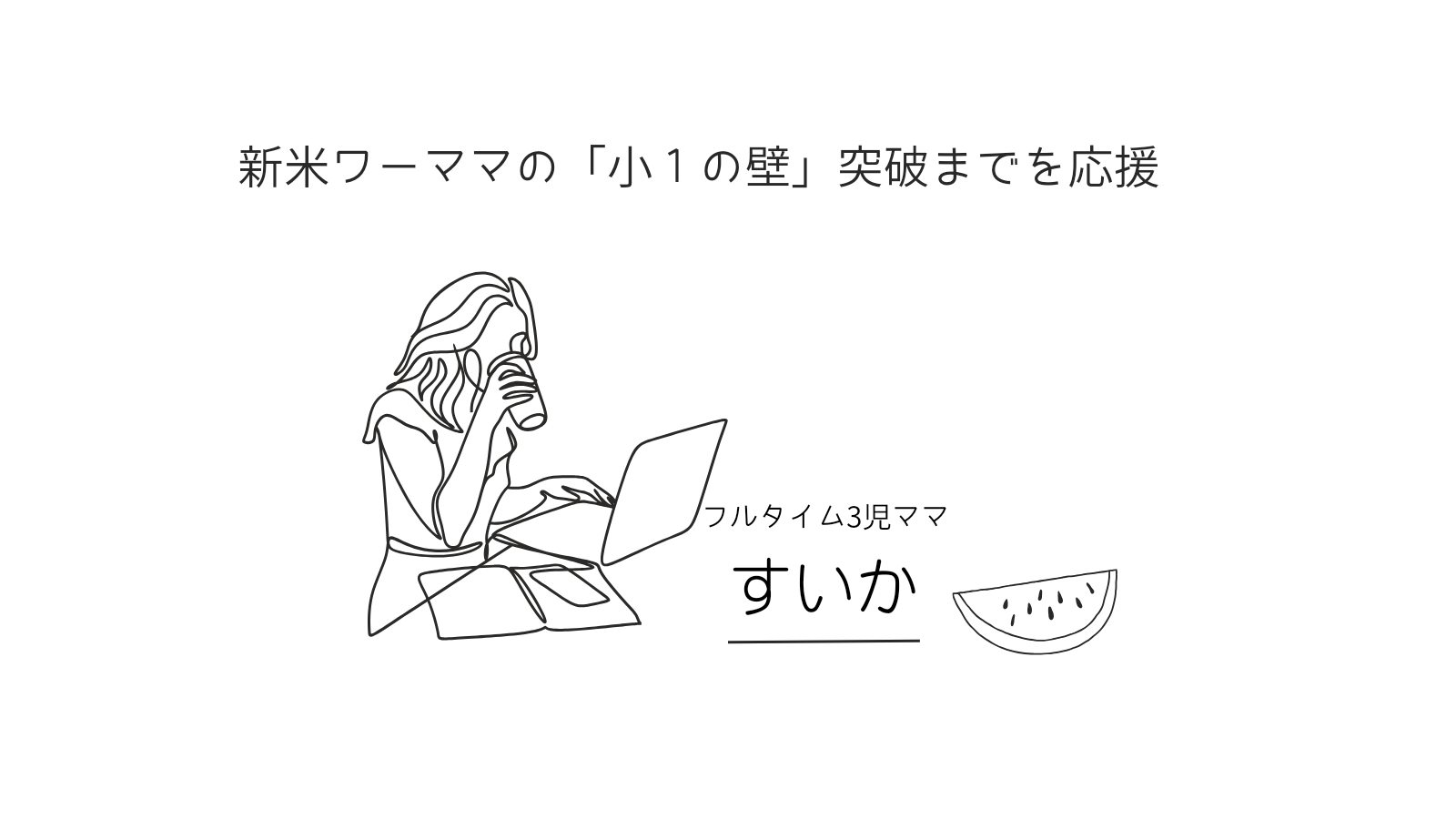
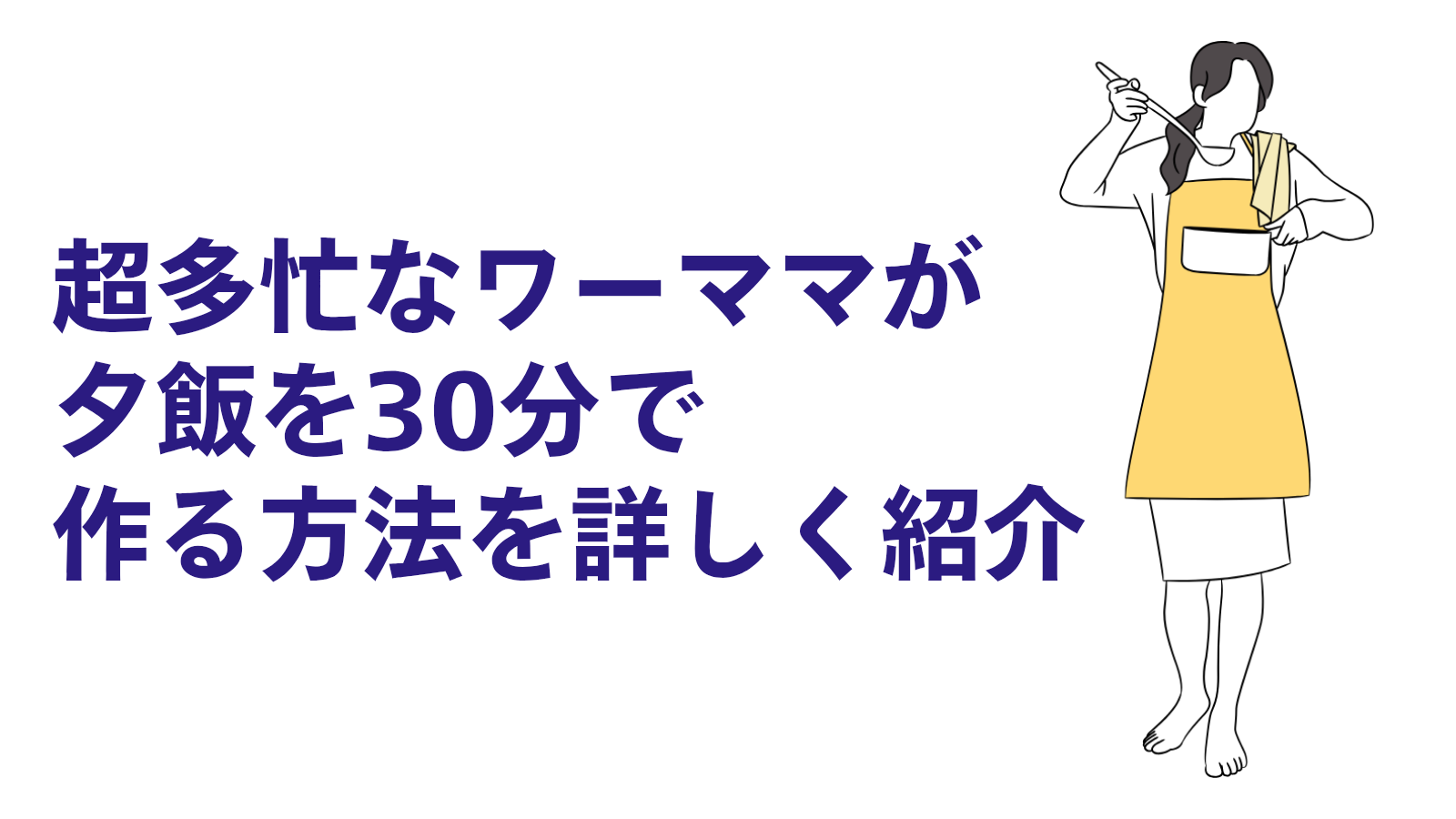
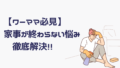
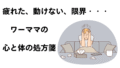
コメント